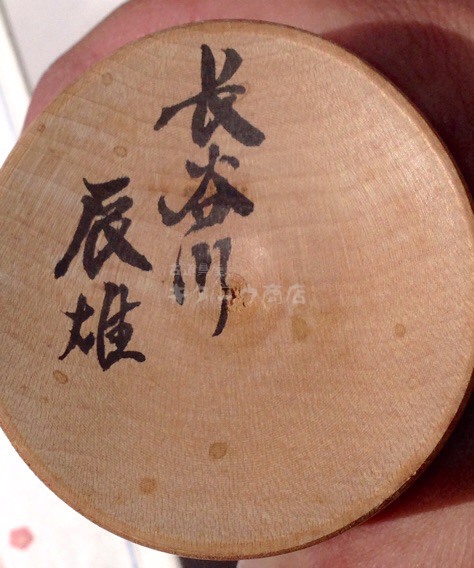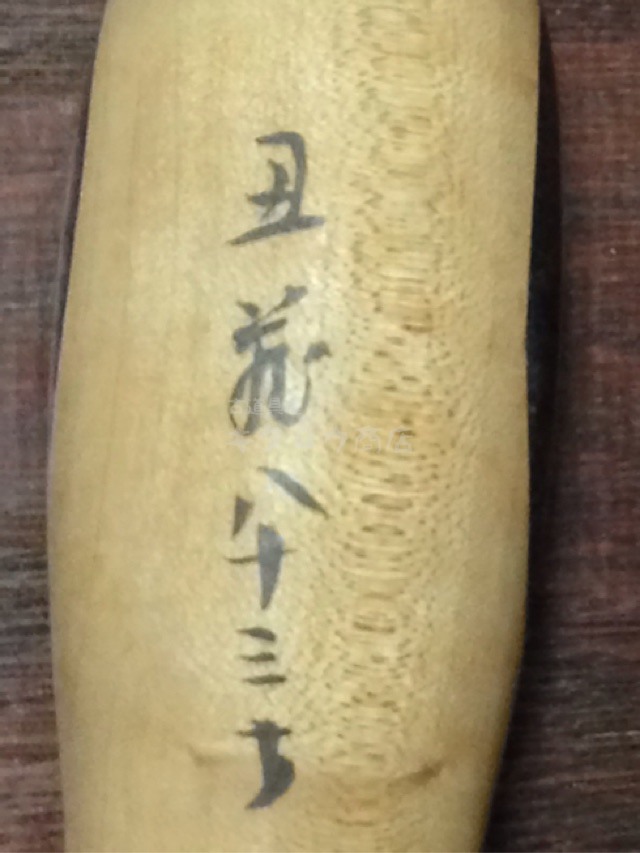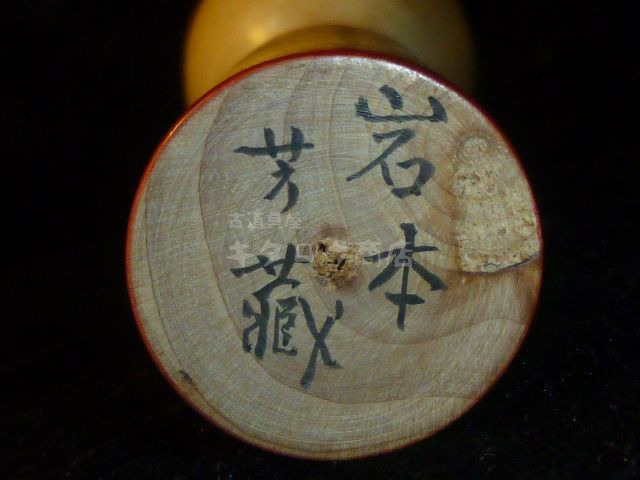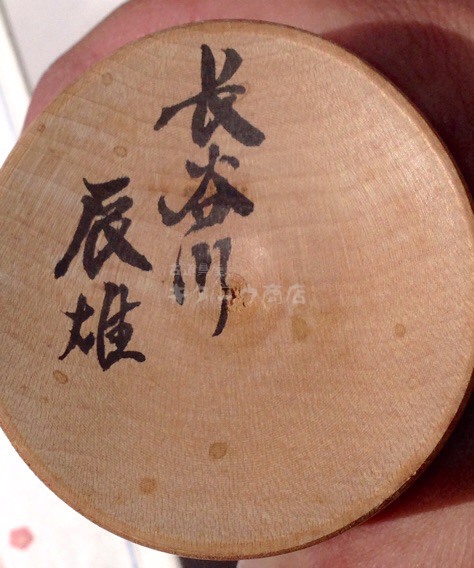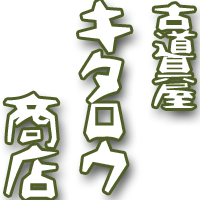岐阜県のお客様より宅配買取にて70本ほどのこけしをご売却いただきました。
佐々木金一郎
津軽系(大鰐)
師匠:佐々木金次郎(父)
大正7年生まれ
昭和50年逝去
津軽のこけしと言えば
黒石の温湯 と
佐々木金一郎の居た大鰐が二大中心地となる。
大鰐は津軽塗 能代塗の下木地産業でも古い歴史がある。
金一郎は最初 父金次郎もそうだったように(金次郎の描彩は長谷川辰雄)
他の大鰐の工人と同じく
自身で描彩はせず家族が書いていた
その後
昭和38~39年頃より自身でも描彩を書くようになったようである。
そのことについて 大正の中期頃までは
真相はわかりませんが
大鰐の工人はこけしには描彩無いものと信じており
その後、大正時代末期頃
あの長谷川辰雄によって多彩な描彩がはじまり
木地工人は辰雄に描彩の依頼をし
昭和初期頃までは大鰐の描彩の九割は辰雄の手によるものとの
逸話もあります。


岐阜県のお客様より宅配買取にて70本ほどのこけしをご売却いただきました。
佐藤丑蔵 (地蔵型)
遠刈田系(肘折系との見方もあり)
師匠:佐藤文六(叔父)
明治32年生まれ
昭和61年逝去
遠刈田に生まれ工人となった後の明治末より
肘折・及位・湯田など各地を放浪
昭和20年以降に遠刈田に戻る
この頃より本人型は明治大正昭和型といわれる型の他
師匠の型である文六型・辻右衛門型など十種を超えるという
中には 当時のTVに登場した人物 佐藤栄作 大平正芳 などの政治家から
笑福亭仁鶴 松村英子などのタレントをモデルとした作も存在
生涯 自由奔放の工人であった。
文部大臣奨励賞受賞

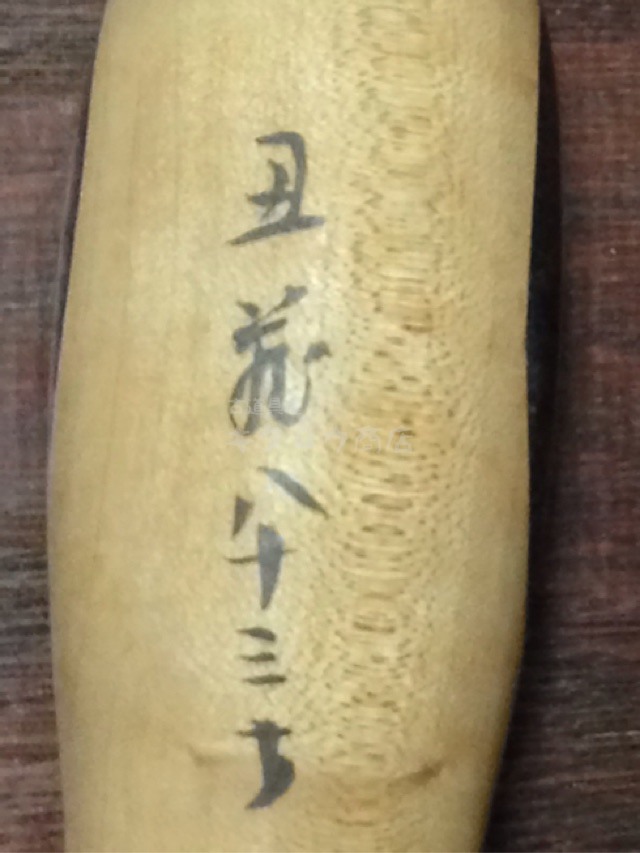
岐阜県のお客様より宅配買取にて70本ほどのこけしをご売却いただきました。
佐藤善二
津軽系
師匠:盛秀太郎
大正14年生まれ
昭和60年逝去
昭和31年頃より盛秀太郎に師事し33年頃独立
自身型の他 斎藤幸兵衛型 佐藤伊太郎型なども作る。
毎日新聞社賞受賞


岐阜県のお客様より宅配買取にて70本ほどのこけしをご売却いただきました。
岩本芳蔵工人
土湯系 中の沢系
師匠:岩本善吉
明治45年(大正元年)生まれ
昭和48年逝去
十代の前半頃 磯谷直行 佐藤豊治に木地を習うが、十六歳の頃出奔、その後昭和7年に中の沢に戻る。
昭和8年頃よりこけしの製作を再開。
再開後は父、善吉型は作らなかったが、昭和31年になり小野洸の父善吉型(タコ坊主)の復活を懇願し、タコ坊主が直系の芳蔵の手により復活。
芳蔵の手によるタコ坊主は晩年の9年間のみ制作されたそうである。
なお芳蔵の死後昭和49年
芳蔵の弟子たちにより「たこ坊主会」が組織され継承されてきました。
現在では継承する工人が少なくなったとはいえ、まだまだ「たこ坊主」は生き続けております。

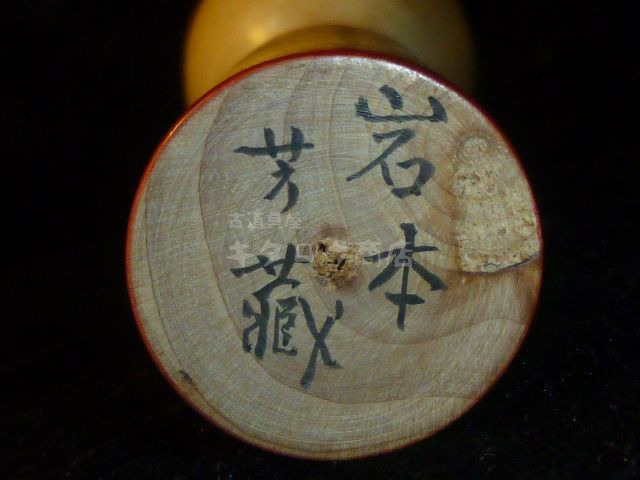

滋賀県のお客様より宅配買取にて70本ほどのこけしをご売却いただきました。
長谷川辰雄工人
津軽系
師匠:佐々木金次郎・島津彦作
明治38年生まれ
昭和60年逝去
大正10年頃より兄、金次郎に木地を学び
その後、島津彦作に師事
昭和初期頃には兄、金次郎をはじめ 村井福太郎 間宮明太郎のこけしにも描彩
昭和33年より一時制作を休止後39年復活。
朝日新聞社賞受賞